自然言語処理と分布仮説について
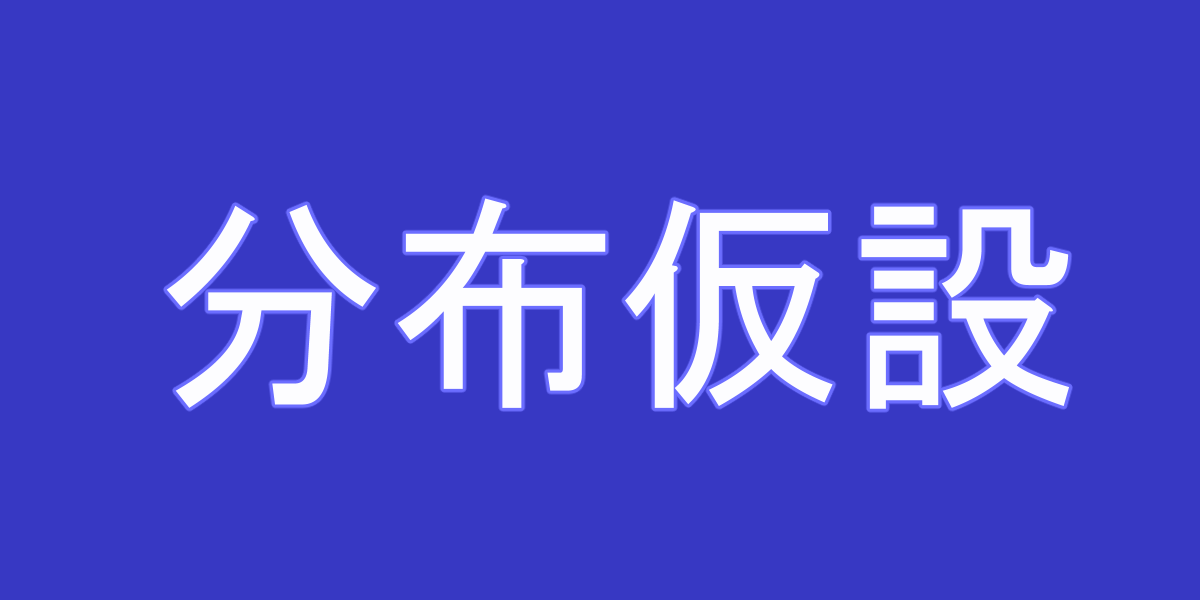
1. 分布仮説とは
分布仮説(Distributional Hypothesis)とは、単語の意味はその単語が文脈内でどのように使われるかに依存しているという考え方です。この仮説は、分散表現や単語埋め込みに関連しており、単語の意味をその分布(他の単語との共起)によって捉えるというアイデアに基づいています。
簡単に言えば、「似たような意味を持つ単語は、似たような文脈で使われる傾向がある」ということです。この考え方は、自然言語処理技術の多くに応用されており、Word2VecやBERTなどのモデルで使われています。
「eat」と「devour」のように、文脈が似ていることで意味が近いと考えられる別の単語のペアをいくつか挙げてみます。
2. 分布仮説の具体例
2.1. 「eat」と「devour」
- “I eat an apple.”
- “I eat a sandwich.”
- “I devour an apple.”
- “I devour a sandwich.”
![]()
![]()
![]()
2.2. 「look」と「gaze」
- “I look at the sky.”
- “I look at the painting.”
- “I gaze at the sky.”
- “I gaze at the painting.”
「look」と「gaze」はどちらも「見る」という意味がありますが、「gaze」は「じっと見つめる」という意味を持ちます。どちらも視覚に関連する文脈で使われるため、意味が近い単語と考えられます。
2.3. 「talk」と「chat」
- “I talk with my friend.”
- “I talk about the movie.”
- “I chat with my friend.”
- “I chat about the movie.”
「talk」と「chat」はどちらも「話す」という意味を持ちますが、「chat」は「気軽に話す」「おしゃべりする」というニュアンスがあります。どちらも会話に関連する文脈で使われるため、意味が近いとみなされます。
2.4. 「run」と「sprint」
- “I run to the store.”
- “I run every morning.”
- “I sprint to the store.”
- “I sprint every morning.”
「run」と「sprint」はどちらも「走る」という意味を持ちますが、「sprint」は「全力で走る」「短距離を走る」という意味があります。どちらも運動に関連する文脈で使われるため、意味が近い単語と言えます。




