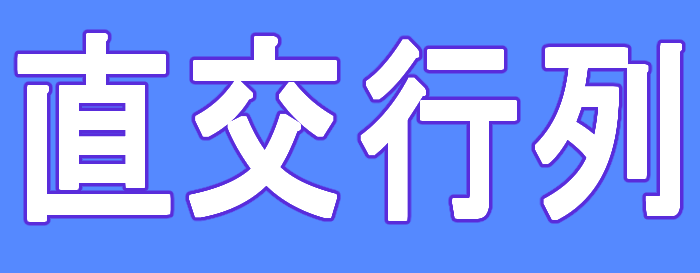線形写像の定義・具体例・例題について

1. 線形写像とは
- 加法の保存:2つのベクトル \( \mathbf{x}, \mathbf{y} \) に対して、\[ f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) \]
- スカラー倍の保存:任意のスカラー \( c \) とベクトル \( \mathbf{x} \) に対して、\[ f(c\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x}) \] これは、ベクトルのスカラー倍をそのまま写像後のスカラー倍に対応させることを意味します。
2. 線形写像の具体例
\( \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \) の線形写像 \( f \) の具体例を示します。
2.1. 例 1: 回転行列を用いた線形写像
線形写像 \( f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \) は、ベクトル \( (x, y) \) を角度 \( \theta \) だけ回転させる写像として定義できます。
\[ f\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \]
例えば、\( \theta = \frac{\pi}{4} \) の場合、45度回転する写像になります。
\[ f\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x – y}{\sqrt{2}} \\ \frac{x + y}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \]
2.2. 例 2: 拡大・縮小行列を用いた線形写像
拡大・縮小を表す線形写像も定義できます。
\[ f\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ 3y \end{bmatrix} \]
この写像は、x方向に2倍、y方向に3倍に拡大する写像です。
2.3. 例 3: シアー変換(せん断変換)
せん断変換を表す線形写像もあります。
\[ f\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \\ y \end{bmatrix} \]
この写像は、x軸方向にyの量だけずらすせん断変換です。
3. 例題
3.1. 例題1:\( f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \)
\[ f\left( \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2x_1 – x_2 \\ 3x_1 + 4x_2 \\ x_1 + 5x_2 \end{bmatrix} \]
加法性の性質を確認をします。
\( \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \) とすると、
\[ f\left( \mathbf{u} + \mathbf{v} \right) = f\left( \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2(u_1 + v_1) – (u_2 + v_2) \\ 3(u_1 + v_1) + 4(u_2 + v_2) \\ (u_1 + v_1) + 5(u_2 + v_2) \end{bmatrix} \] \[ = \begin{bmatrix} 2u_1 – u_2 \\ 3u_1 + 4u_2 \\ u_1 + 5u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2v_1 – v_2 \\ 3v_1 + 4v_2 \\ v_1 + 5v_2 \end{bmatrix} = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \]
よって、加法性が成り立ちます。
スカラー倍の性質を確認をします。
\( \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \) とすると、
\[ f(\alpha \mathbf{u}) = f\left( \begin{bmatrix} \alpha u_1 \\ \alpha u_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2(\alpha u_1) – (\alpha u_2) \\ 3(\alpha u_1) + 4(\alpha u_2) \\ (\alpha u_1) + 5(\alpha u_2) \end{bmatrix} \] \[ = \alpha \begin{bmatrix} 2u_1 – u_2 \\ 3u_1 + 4u_2 \\ u_1 + 5u_2 \end{bmatrix} = \alpha f(\mathbf{u}) \]
よって、スカラー倍も成り立ちます。
この写像 \( f \) は、加法性とスカラー倍の両方の条件を満たしているため、線形写像です。
3.2. 例題2:\( f: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2 \)
\[ f\left( \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3x_1 – 2x_2 + x_3 \\ -x_1 + 4x_2 + 5x_4 \end{bmatrix} \]
加法性の性質を確認をします。
\( \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} \) とすると、
\[ f\left( \mathbf{u} + \mathbf{v} \right) = f\left( \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \\ u_4 + v_4 \end{bmatrix} \right) \] \[ = \begin{bmatrix} 3(u_1 + v_1) – 2(u_2 + v_2) + (u_3 + v_3) \\ -(u_1 + v_1) + 4(u_2 + v_2) + 5(u_4 + v_4) \end{bmatrix} \] \[ = \begin{bmatrix} 3u_1 – 2u_2 + u_3 \\ -u_1 + 4u_2 + 5u_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3v_1 – 2v_2 + v_3 \\ -v_1 + 4v_2 + 5v_4 \end{bmatrix} = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \]
よって、加法性が成り立ちます。
スカラー倍の性質を確認をします。
\( \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} \) とすると、
\[ f(\alpha \mathbf{u}) = f\left( \begin{bmatrix} \alpha u_1 \\ \alpha u_2 \\ \alpha u_3 \\ \alpha u_4 \end{bmatrix} \right) \] \[ = \begin{bmatrix} 3(\alpha u_1) – 2(\alpha u_2) + (\alpha u_3) \\ -(\alpha u_1) + 4(\alpha u_2) + 5(\alpha u_4) \end{bmatrix} \] \[ = \alpha \begin{bmatrix} 3u_1 – 2u_2 + u_3 \\ -u_1 + 4u_2 + 5u_4 \end{bmatrix} = \alpha f(\mathbf{u}) \]
よって、スカラー倍も成り立ちます。
この写像 \( f \) は、加法性とスカラー倍の両方の条件を満たしているため、線形写像です。